第4章|実名議員と派閥の関係まとめ(完全版)55歳
裏金問題の核心にあるのは、「派閥ぐるみ」で仕組まれた資金スキームだ。本章では、具体的に誰が関わっていたのか、どの派閥がどれだけ深く組み込まれていたのかを、可能な限り実名で紹介し、この問題の実態と深さを明らかにしていく。
◼︎ 安倍派(清和政策研究会):裏金構造の中枢
安倍派は、この裏金事件の“心臓部”とも言える存在だった。パーティー収入のノルマ制度を構築し、超過分を記録せず、現金で議員に“配布”するスキームは、極めて巧妙かつ組織的だった。
- 塩谷立(元文科相/派閥幹部)…会計に最も近く、数千万円の資金移動に関与した可能性。
- 下村博文(元文科相)…赤坂の事務所に家宅捜索が入った“現場”。幹部中の幹部。
- 松野博一(元官房長官)…岸田内閣の屋台骨。記者会見での「詳細は控える」に国民は激怒。
- 西村康稔(元経済再生担当相)…感染対策で全国に知られた人物も“裏金議員”の一人。
- 世耕弘成(元経産相)…参院の大幹部。裏金疑惑により辞任するも、処罰はなし。
安倍派の関与金額は、報道によれば2.5億円超。関係者は40人以上にのぼる。
◼︎ 二階派(志帥会):金の流れは封建的
元幹事長の二階俊博をトップとするこの派閥は、上下関係が明確な“封建的構造”で、若手議員にパー券ノルマを課し、忠誠の証として金を受け取るような空気があった。
- 小泉龍司…ノルマ制下で多額の券販売。収支報告書に記載されなかった金額の存在を認めた。
- 宮内秀樹…農政に明るいとされる人物だったが、裏金問題で一転して“黒い政治家”のイメージに。
二階派は人数規模で安倍派に劣るが、関与金額は1億円弱。裏金“発注元”としての責任は重い。
◼︎ 岸田派(宏池会):首相の派閥でも不正が蔓延
現職の岸田文雄首相が率いていたこの派閥からも、記載漏れが続々と判明した。
- 2024年、岸田首相は派閥解散を表明するも、「知らなかった」「責任は会計にある」の姿勢を崩さず。
- 派閥所属の複数議員が事情聴取を受けるも、すべて不起訴。首相への影響を恐れた検察の“忖度”と批判される。
第5章|なぜ“犯罪にならない”?政治資金規正法の腐敗保護構造

政治資金規正法は、本来なら政治資金を透明にし、汚職を防ぐための法律だ。しかし実際には、この法律そのものが“腐敗を守る盾”として機能している。
◼︎ 実質的に「記載しなくてもいい」抜け道
- 20万円未満は記載不要:企業や団体が寄付を19万円ずつ何度でも行えば、名前を隠せる。
- 訂正すれば罪に問われない:後で「ミスでした」と言えば、違法ではなくなる。
- 形式犯としての扱い:刑事罰ではなく“行政処分”にとどまるケース多数。
◼︎ 責任は秘書へ、議員はノーダメージ
特に悪質なのは、“秘書”というワンクッションを置くことで、議員本人が責任を回避できる構造だ。
- 例えば、松野官房長官の件では、記載漏れを“元秘書の処理ミス”と説明。
- 東京地検は議員本人の立件を見送り、秘書のみを略式起訴。
これは明らかに、政治家だけが法律の上に立つ異常事態である。
◼︎ 実質的に「犯罪ではない」扱いが腐敗を助長
- 民間人ならば、脱税や粉飾決算で厳罰。
- 政治家なら「記載漏れ」でOK。
この“二重基準”が、国民の政治不信の核心である。
第6章|裏金は国政だけではない──自治体レベルにも広がる腐敗
2024年、東京都議会で発覚した裏金問題は、裏金スキームが地方政治にも根を張っていることを証明した。
◼︎ 都議会自民党:パー券記載漏れ3500万円
- 都議会自民党の複数議員が、パーティー券の収入の一部を収支報告書に記載せず。
- 2021年から2023年にかけて、計約3500万円分が未記載。
- 「販売ノルマを超えた分は記載しない」という安倍派と同じ構造が使われていた。
◼︎ 再選された“裏金議員”の実態
- 問題が明るみに出たにもかかわらず、都議選では記載漏れ議員26人中17人が再選。
- 世論の関心が地方議会まで届いていない証拠。
- 都議会自民党幹部は「政治資金の透明性向上に努める」とコメントしたが、具体策はなし。
◼︎ 他の地方議会でも構造は同じ可能性
- 自民党は全国の都道府県議会・市町村議会においても最大会派であり、同様の“慣習”が横行している恐れがある。
- 地方では記者クラブも限られ、メディア監視の目が届きにくい。
- 一部のNPOや市民団体が情報公開請求を進めているが、抵抗も根強い。
◼︎ 腐敗の根は“足元”にもある
我々国民は、中央の政治家にばかり目を向けがちだが、 実際には地方議会でも、同じ構造の“裏金政治”が静かに蔓延している。
政治を変えるなら、まずは足元から。 「市議」「県議」にも、鋭い目を向けるべき時が来ている。
第4章まとめ|実名議員と派閥の関係 ― 腐敗は“派閥ぐるみ”
- 自民党の主要派閥(安倍派・二階派・岸田派)すべてが裏金スキームに関与。
- 中心となったのは安倍派(2.5億円規模、関係議員40人以上)。
- 実名が挙がったのは塩谷立、松野博一、西村康稔、世耕弘成、下村博文ら有力者ばかり。
- 議員は「秘書がやった」と責任回避、不起訴多数。
- 「記載漏れ」では済まされない。これは明確な組織的隠蔽行為。
第5章まとめ|なぜ犯罪にならない? ― ザル法と“責任逃れ”構造
- 政治資金規正法が“記載すればOK”の抜け穴だらけのザル法。
- 20万円未満の寄付は記載不要。訂正すれば処罰されない。
- 議員は責任を秘書に押し付けることで罪を逃れている。
- 民間なら脱税・粉飾で逮捕されるが、政治家は無罪放免。
- この“二重基準”こそが、国民の政治不信の源。
第6章まとめ|地方にも広がる裏金構造 ― 都議会で再選された裏金議員たち
- 東京都議会自民党でも3500万円以上の裏金が発覚。
- 議員26人中17人が問題後も再選され、議場に戻ってきている。
- 地方もパーティー券ノルマ制度が常態化していた疑い。
- 地方政治は監視が甘く、腐敗の温床になっている可能性が高い。
- 国政だけでなく、“足元の政治”にも厳しい目が必要。
投稿者コメント
これが現実です。
名前を出せば終わりじゃない。仕組みを暴かなければ何も変わらない。
政治資金規正法という“ザル法”に守られ、裏金を作っても捕まらない。
それどころか再選までされる。
中央の議員も、地方の議員も、
何も説明せずに居座り続ける——この国の政治は、いつからこんなに腐ったのか?
でも、一番危険なのは、
「どうせ何も変わらない」と諦めてしまうこと。
腐敗は続く。選挙は来る。
だから、今こそ“見てしまったあなた”にしかできない選択がある。




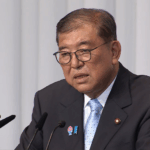


コメント